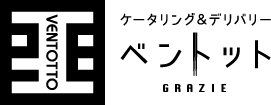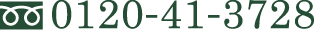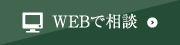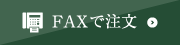長寿のお祝いは、40歳以降の10歳ごとに祝う中国の風習が日本に伝わったものといわれています。
室町時代には現在のような形になり、一般の間にもひろまったのは江戸時代ごろだそうです。
| 長寿歴 | よみ | 数え年 | 満年齢 | 意味・由来 | 基調色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 還暦 | かんれき | 61 | 60 | 数え年61歳になると生まれた年の干支に還るから | 赤 |
| 緑寿 | ろくじゅ | 66 | 65 | 66歳は緑緑となるため。日本百貨店協会が提唱。 | 緑 |
| 古希 | こき | 70 | 69 | 唐の詩人、杜甫の「人生七十年古来稀なり」の一節から | 紫 |
| 喜寿 | きじゅ | 77 | 76 | 「喜」の草書体が七を三つ書くことから | 紫 |
| 傘寿 | さんじゅ | 80 | 79 | 「傘」の略字が八十に見えることから | 金茶 |
| 半寿 | はんじゅ | 81 | 80 | 「半」の字が八十一に見えることから | 金茶 |
| 米寿 | べいじゅ | 88 | 87 | 「米」の字を分解すると八十八になることから | 金茶 |
| 卒寿 | そつじゅ | 90 | 89 | 「卒」の略字が九十に見えることから | 白 |
| 白寿 | はくじゅ | 99 | 98 | 「百」から「一」を取ると「白」になるため | 白 |
| 百寿 | ももじゅ | 100 | 99 | 文字通り「百」だから。「百賀(ももが)の祝い」とも言う | |
| 茶寿 | ちゃじゅ | 108 | 107 | 「茶」の文字が八十八に「十」が2つのっているように見えるから | |
| 珍寿 | ちんじゅ | 110 | 109 | 珍しいほどの長寿という意味。珍寿は数え年112歳以上というところもある | |
| 皇寿 | こうじゅ | 111 | 110 | 「皇」の字を分解すると「白」「一」「十」「一」となり、組み合わせ直すを「百十一」となるため | |
| 大還暦 | だいかんれき | 120 | 119 | 還暦の倍の意味 |
長寿のお祝いは、高齢者の賀寿への健康的な気遣いから昔通りに数え年で祝う方が多いようです。
ただし、還暦だけは数え年で61歳、満年齢60歳でお祝いします。